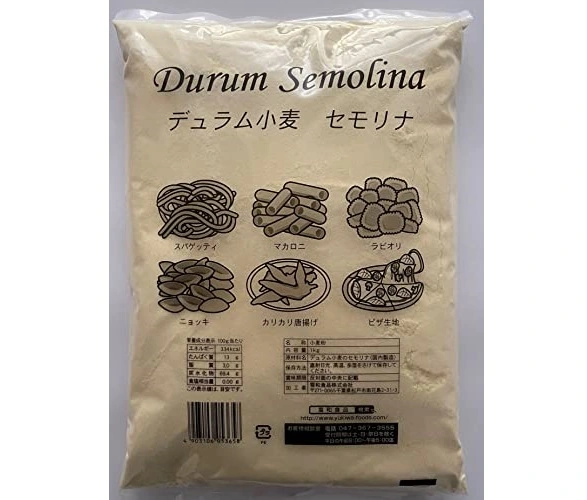「柳井答弁」から見る国際法上の個人請求権 - 全てはここから始まった
2021-10-19 カテゴリー:慰安婦問題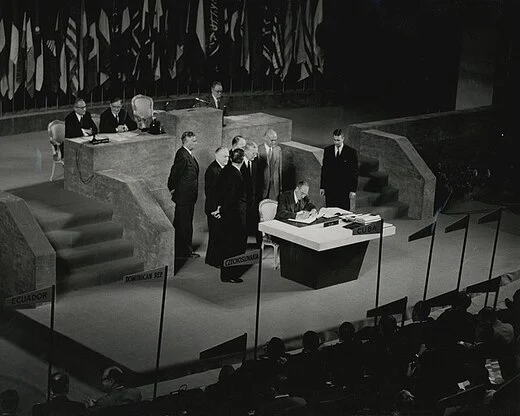
Photo by U.S. Department of State (licensed under CC0 1.0)
クリック応援よろしくお願いします。
国際法上の個人請求権
日韓における請求権の問題は1991年の柳井俊二条約局長の柳井答弁を受けて活発化する。原爆被害者が日本政府に対して、サンフランシスコ講和条約で個人の請求権を放棄したことに対する訴えに対し、米国に対する個人の請求権は消滅しない、外交保護権を国が放棄したものだと答弁している。
日韓は互いに外交保護権を放棄
国際法上、国家による不法行為下の請求権は消滅しない。この立場は日本が示したものであり、同時に日韓の間においても、個人の請求権は消滅せず、国家間の外交保護権を放棄したという見解を示したものだ。
反日賠償請求のスタート
この答弁を聞いてから韓国の反日運動は賠償請求運動に変化する。外交保護権や個人賠償請求手続きなどについては全く理解しておらず、ただ大声をあげて要求して来た。
外相ですら理解していない
康京和元外交部長はBBCのインタビューに対して、1990年代前半では日本政府は同じ考えを示していたが、後に変節したと答えていたが、日本の国際法上の立場は変わっていない。
ここからも、彼女は全く理解していないことが分かる。個人の請求に対して国は関与しない。日本政府に強制力を持つ命令が出来るのは日本の司法以外に存在しない。
個人が日本の司法で訴えを起こす以外に無い
慰安婦や徴用工に残された個人の請求権は、日本の司法に訴え出るしか方法は無い。原爆被害者は個人として米国司法に訴えを起こす以外に方法は無い。柳井答弁はそのことを説明したものだ。
韓国大法院などの司法は国家による不法行為説に立脚して判決を下している。
日本は日韓併合の不法性、強制連行という不法行為についても認めていない。よって消滅時効により訴えは却下されることが予想される。